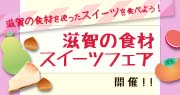白菜の大きさは愛情に比例する~白菜~
12月21日の放送でご紹介した食材は白菜でした。

ふだん我が家の食卓にも並ぶこの真ん中が黄色い白菜。
正確には「黄芯白菜」というそうです。

私もそうですけど、
皆さんこれを単に「白菜」と呼んでいると思いますが、
さすが生産者の黒川實さんは
ちゃんと「黄芯白菜」と区別して呼んでいらっしゃいます。
※大きく分けて、黄芯白菜と、漬物などによく用いられる白芯白菜がある。

今の季節、鍋物をはじめ、様々な料理で活用される白菜。
黒川さんに美味しい白菜の見分け方 を伺ってみました。
を伺ってみました。
「固くて締まったものがいい!」
実際、半分に切ってもらってみたのが上の写真。
葉っぱが隙間なくぎっしり詰まって、今にもはちきれんばかり
「シャキシャキ感が出て美味しいんや!」
ただ、そのまま育てたのでは、
葉は外へ広がろうとするので、なかなかうまく締まりません

中には上部を紐でくくって締める農家もいらっしゃるそうですが、
黒川さんは、葉が内側に締まるように
毎日一株一株両手で包み押さえて廻るそうです
白菜だって生き物ですから、
紐で縛られるよりかは、
人の手に触れて育つ方が愛情 を感じるのか
を感じるのか
この白菜もよく締まってると黒川さんは言います。
これまでのインタビューで
事あるごとに話題に挙がるのが虫
「農薬が撒けないので防虫対策には苦労する」と、
しばしば悪者扱いされがちな虫ですが
しかし黒川さんから意外なお言葉が!
「でも虫は賢いんや!」
ん どういうこと
どういうこと
確かに虫は白菜の葉を食べるけど、必ず葉は外側から食べていく。
でも内側の芯の部分には、まず手をつけない。
それは、芯には来年の芽 になる種の部分があるからで、
になる種の部分があるからで、
虫もちゃんとそれを理解して、そこを残して食べている。
だから虫は賢いんやと。

よく見ると、葉が食われて部分は確かに外側で、内側は無事。
収穫も、食われていない内側を刈り取るので問題はないのです。
「そもそも虫も食わんような白菜は
美味しくない!」
うん、納得のご意見です
ところで、
台風の最中、田畑を見に行って事故に遭う方のニュース を時折見かけます。
を時折見かけます。
しかし、黒川さんがおっしゃるには、
「自分が手塩にかけた大切な作物が
気になって気になって居たたまれなくて、
それで周囲の反対を押し切って行っちゃうんや」
自分で育てた作物への愛情が大きい人 ほど
ほど
そういう気持ちになりやすく、
黒川さんご自身もその気持ちはよく分かるそうです。

この話を伺い、私は目からウロコが落ちました

事故自体は痛ましいものですが、
農家の皆さんが作物に懸ける愛情の大きさに胸を打たれました
(※とはいえ農家の皆さん、くれぐれも無理はされないように… )
)
旬の時季に旬の食材を提供するのが農家の務め
と、おっしゃる黒川さん。
そのための労苦をいとわない姿は、
このコーナーの最終回に相応しい“農家の鑑”のような方でした
以上で、この「生産者の声」ブログも終了です
貴重なお話をしてくださった生産者の皆さん、
そしてこの取材ブログをこれまでお読みいただいた皆さん、
ありがとうございました!
ふだん我が家の食卓にも並ぶこの真ん中が黄色い白菜。
正確には「黄芯白菜」というそうです。
私もそうですけど、
皆さんこれを単に「白菜」と呼んでいると思いますが、
さすが生産者の黒川實さんは
ちゃんと「黄芯白菜」と区別して呼んでいらっしゃいます。
※大きく分けて、黄芯白菜と、漬物などによく用いられる白芯白菜がある。

今の季節、鍋物をはじめ、様々な料理で活用される白菜。
黒川さんに美味しい白菜の見分け方
 を伺ってみました。
を伺ってみました。「固くて締まったものがいい!」
実際、半分に切ってもらってみたのが上の写真。
葉っぱが隙間なくぎっしり詰まって、今にもはちきれんばかり

「シャキシャキ感が出て美味しいんや!」
ただ、そのまま育てたのでは、
葉は外へ広がろうとするので、なかなかうまく締まりません


中には上部を紐でくくって締める農家もいらっしゃるそうですが、
黒川さんは、葉が内側に締まるように
毎日一株一株両手で包み押さえて廻るそうです

白菜だって生き物ですから、
紐で縛られるよりかは、
人の手に触れて育つ方が愛情
 を感じるのか
を感じるのかこの白菜もよく締まってると黒川さんは言います。
これまでのインタビューで
事あるごとに話題に挙がるのが虫

「農薬が撒けないので防虫対策には苦労する」と、
しばしば悪者扱いされがちな虫ですが
しかし黒川さんから意外なお言葉が!
「でも虫は賢いんや!」
ん
 どういうこと
どういうこと
確かに虫は白菜の葉を食べるけど、必ず葉は外側から食べていく。
でも内側の芯の部分には、まず手をつけない。
それは、芯には来年の芽
 になる種の部分があるからで、
になる種の部分があるからで、虫もちゃんとそれを理解して、そこを残して食べている。
だから虫は賢いんやと。
よく見ると、葉が食われて部分は確かに外側で、内側は無事。
収穫も、食われていない内側を刈り取るので問題はないのです。
「そもそも虫も食わんような白菜は
美味しくない!」
うん、納得のご意見です

ところで、
台風の最中、田畑を見に行って事故に遭う方のニュース
 を時折見かけます。
を時折見かけます。しかし、黒川さんがおっしゃるには、
「自分が手塩にかけた大切な作物が
気になって気になって居たたまれなくて、
それで周囲の反対を押し切って行っちゃうんや」
自分で育てた作物への愛情が大きい人
 ほど
ほどそういう気持ちになりやすく、
黒川さんご自身もその気持ちはよく分かるそうです。
この話を伺い、私は目からウロコが落ちました


事故自体は痛ましいものですが、
農家の皆さんが作物に懸ける愛情の大きさに胸を打たれました

(※とはいえ農家の皆さん、くれぐれも無理はされないように…
 )
)旬の時季に旬の食材を提供するのが農家の務め

と、おっしゃる黒川さん。
そのための労苦をいとわない姿は、
このコーナーの最終回に相応しい“農家の鑑”のような方でした

以上で、この「生産者の声」ブログも終了です

貴重なお話をしてくださった生産者の皆さん、
そしてこの取材ブログをこれまでお読みいただいた皆さん、
ありがとうございました!

丹波には負けないぞ!~湖北の黒豆~
12月14日の放送でご紹介した食材は黒豆でした。

もう黒豆が欠かせないおせちの季節ですね
生産者の嶋崎善弘さんに伺ったところ
やはりおせちで黒豆を食べる人が多いので、
年末に向かって一番需要も高くなるそうですが、
嶋崎さんは「年間を通して供給したい」という思いがあり、
計画的に出荷されています。

とはいえ、収穫時期は12月前半がピーク
黒豆は、6月中旬に種を蒔き、
9~10月になるとサヤに実をつけます。

これがだんだんと枯れて固くなり、

サヤを振ってみて、中の実がカタカタと音が鳴ると
いよいよ収穫の合図!

一気にたくさん収穫するには、やはりコンバイン!

今の時代、コンバインで収穫すると
自動でサヤから豆を取り出してくれます


これを天日で乾燥させます

そうすると、あれよあれよと
こんなに小さくなっちゃうんです

(左)乾燥した黒豆 (右)乾燥していない黒豆
これを今度は機械で粒の大きさごとにふるいにかけます。

ここまでは自動。
しかし次の工程「選別」は違います!
選別とは、
ふるいにかけた黒豆に傷みがないかをチェックする作業のこと。
こればかりは機械に頼らず、
人の目 で1粒1粒チェックしていきます
で1粒1粒チェックしていきます

この作業は、嶋崎さんのお母さん圀枝さんのお仕事!
目で見て、手で触ってしっかり選別していきます。

「肩がこる仕事やけぇ」と圀枝さん
あとは袋詰めして出荷するのみ。

豆は乾燥しているので、もちろん長期保存が出来ます
なので、年間を通じて安定した供給のために
出荷量を調整しながら、翌年の秋ごろまで出荷されています。
そしてまた次のシーズンがやってくるのです。
黒豆は、年間通じて需要があるそうですが、
7~8月になるとその需要もガクッと下がる そうです。
そうです。
しかし秋 になってくると
になってくると
みな豆を欲してくるのか、一気に需要も高くなり
最盛期のおせちシーズンに突入 となるわけです。
となるわけです。
ただこの黒豆、
実はいま密かに話題になっているものがあります。
それは黒豆の枝豆です!

サヤが固く枯れてしまう前に収穫したものがそれです。
普通の大豆の枝豆に比べると
やわらかく甘みがあり、食感も違うと評判の一品
しかも本来は乾燥させた黒豆が主であるところを、
ちょっとつまみ食い したものなので
したものなので
出荷量も時期も限定されるプレミア品なのです!

残念ながら、今は時期が終わったので販売されていません…
興味をもたれた方は、ぜひ来年の秋 までお待ちください
までお待ちください
もう黒豆が欠かせないおせちの季節ですね

生産者の嶋崎善弘さんに伺ったところ
やはりおせちで黒豆を食べる人が多いので、
年末に向かって一番需要も高くなるそうですが、
嶋崎さんは「年間を通して供給したい」という思いがあり、
計画的に出荷されています。

とはいえ、収穫時期は12月前半がピーク
黒豆は、6月中旬に種を蒔き、
9~10月になるとサヤに実をつけます。
これがだんだんと枯れて固くなり、
サヤを振ってみて、中の実がカタカタと音が鳴ると
いよいよ収穫の合図!

一気にたくさん収穫するには、やはりコンバイン!

今の時代、コンバインで収穫すると
自動でサヤから豆を取り出してくれます

これを天日で乾燥させます

そうすると、あれよあれよと
こんなに小さくなっちゃうんです

(左)乾燥した黒豆 (右)乾燥していない黒豆
これを今度は機械で粒の大きさごとにふるいにかけます。

ここまでは自動。
しかし次の工程「選別」は違います!
選別とは、
ふるいにかけた黒豆に傷みがないかをチェックする作業のこと。
こればかりは機械に頼らず、
人の目
 で1粒1粒チェックしていきます
で1粒1粒チェックしていきます
この作業は、嶋崎さんのお母さん圀枝さんのお仕事!
目で見て、手で触ってしっかり選別していきます。
「肩がこる仕事やけぇ」と圀枝さん
あとは袋詰めして出荷するのみ。
豆は乾燥しているので、もちろん長期保存が出来ます

なので、年間を通じて安定した供給のために
出荷量を調整しながら、翌年の秋ごろまで出荷されています。
そしてまた次のシーズンがやってくるのです。
黒豆は、年間通じて需要があるそうですが、
7~8月になるとその需要もガクッと下がる
 そうです。
そうです。しかし秋
 になってくると
になってくるとみな豆を欲してくるのか、一気に需要も高くなり

最盛期のおせちシーズンに突入
 となるわけです。
となるわけです。ただこの黒豆、
実はいま密かに話題になっているものがあります。
それは黒豆の枝豆です!
サヤが固く枯れてしまう前に収穫したものがそれです。
普通の大豆の枝豆に比べると
やわらかく甘みがあり、食感も違うと評判の一品

しかも本来は乾燥させた黒豆が主であるところを、
ちょっとつまみ食い
 したものなので
したものなので出荷量も時期も限定されるプレミア品なのです!
残念ながら、今は時期が終わったので販売されていません…

興味をもたれた方は、ぜひ来年の秋
 までお待ちください
までお待ちください
タグ :第25回長浜まちの駅(黒豆)
農業はリサイクル ~カブラ~
12月7日の放送でご紹介した食材はカブラでした。

生産者の堀井由美子さんに、
どうしてカブラを作りはじめたのか伺ったところ、
「京都の千枚漬や金沢のかぶら寿しが好きで、
京都にも近い大津の地でも栽培できないものか」
と思ったのがきっかけなんだとか。

ご自宅でも毎日様々なお漬物を召し上がっているそうです。
カブラの種まきは、1ヶ所に3粒くらいずつ蒔いていくのですが、
その3粒が生長して、ある程度の大きさになると
そのうちの状態がいい1株だけを残して、他は間引きをしていきます。
しかし、その間引いた株の中でも、生長の見込みのあるものについては、
再度、別の畝に植え直すのだそうです。

収穫するまで多少日数はかかりますが、
それでも立派なカブラとして収穫することが出来ます
堀井さんの畑は周囲をぐるりとネットで囲んでいます。

岩間寺付近の小高い山手にあるので、
鹿や猪といった
野生の動物が畑を荒らすのを防ぐ目的があるそうですが、
脇が散歩道になっているので、
時折心ない人 が作物を盗んでいくのを防ぐ役割もあるそうです。
が作物を盗んでいくのを防ぐ役割もあるそうです。

物が豊かなご時世でも、そういう人がまだいるんですねぇ‥
カブラの収穫というと
童話「おおきなかぶ」 を思い出す人も多いでしょう。
を思い出す人も多いでしょう。

ただ実際のカブラは地表から出ている部分が多いので、
女性の腕でも簡単に引っこ抜くことが出来ます。

この日も立派なカブラを収穫させていただきました

さて、堀井さんの農作業には、ある工夫 が施されています。
が施されています。
この周辺には塵埃処理場(ごみ焼却場)があり、
1200℃で燃やされた木クズなどの灰がたくさん出ます。
その灰を肥料に混ぜて畝に撒くと、
土壌もやわらかくなり、美味しさもUP されるそうです。
されるそうです。

ご近所の方も実践されているそうなので、効果はお墨付き
これぞエコなリサイクル!
ホントに農業には無駄なことがありませんね
生産者の堀井由美子さんに、
どうしてカブラを作りはじめたのか伺ったところ、
「京都の千枚漬や金沢のかぶら寿しが好きで、
京都にも近い大津の地でも栽培できないものか」
と思ったのがきっかけなんだとか。

ご自宅でも毎日様々なお漬物を召し上がっているそうです。
カブラの種まきは、1ヶ所に3粒くらいずつ蒔いていくのですが、
その3粒が生長して、ある程度の大きさになると
そのうちの状態がいい1株だけを残して、他は間引きをしていきます。
しかし、その間引いた株の中でも、生長の見込みのあるものについては、
再度、別の畝に植え直すのだそうです。
収穫するまで多少日数はかかりますが、
それでも立派なカブラとして収穫することが出来ます

堀井さんの畑は周囲をぐるりとネットで囲んでいます。
岩間寺付近の小高い山手にあるので、
鹿や猪といった
野生の動物が畑を荒らすのを防ぐ目的があるそうですが、
脇が散歩道になっているので、
時折心ない人
 が作物を盗んでいくのを防ぐ役割もあるそうです。
が作物を盗んでいくのを防ぐ役割もあるそうです。物が豊かなご時世でも、そういう人がまだいるんですねぇ‥

カブラの収穫というと
童話「おおきなかぶ」
 を思い出す人も多いでしょう。
を思い出す人も多いでしょう。ただ実際のカブラは地表から出ている部分が多いので、
女性の腕でも簡単に引っこ抜くことが出来ます。
この日も立派なカブラを収穫させていただきました

さて、堀井さんの農作業には、ある工夫
 が施されています。
が施されています。この周辺には塵埃処理場(ごみ焼却場)があり、
1200℃で燃やされた木クズなどの灰がたくさん出ます。
その灰を肥料に混ぜて畝に撒くと、
土壌もやわらかくなり、美味しさもUP
 されるそうです。
されるそうです。
ご近所の方も実践されているそうなので、効果はお墨付き

これぞエコなリサイクル!
ホントに農業には無駄なことがありませんね

(辛み⇔甘み)=旨み ~伊吹大根~
11月30日の放送でご紹介した食材は、伊吹大根でした。

名前からも分かるように、滋賀県北東部にある
県内で一番高い伊吹山(1377m)の一帯で栽培されています。

古くは江戸時代の書物にもその名が記されているという伊吹大根は、
「峠の大根」として、現在の米原市大久保地区(旧伊吹町)周辺で
主に自家用に小規模で栽培されてきた作物だそうです。

しかし品種改良された大根が普及すると、
伊吹大根を栽培する農家は減少 していったといいます。
していったといいます。
そんな中、生産者の前澤 静尾さんは、
この伊吹大根の種を守り、現在まで栽培を続けて来られました

栽培歴はもう50年を数えるそうです!
伊吹大根の最大の特徴は、やはり何といっても辛み!
特に大根おろしにすると、さらに辛みが際立ち、
同じく伊吹名産の「伊吹そば」との相性はバツグン

前澤さんの話では
「平地ではなかなかこの辛みは出ない」のだとか。
標高が高い所は昼夜の気温差があり、
平地の大根に比べてゆっくり生長することで
辛みの強い大根が出来るそうです。

またこの短小で寸胴な形も、辛みにとっては重要で、
大きくなればなるほど、辛みは薄まっていくのです。
化学肥料などを与えれば、もっと大きな伊吹大根も穫れるそうですが、
「出来るだけ大きくならないようにする」のが
前澤さんのこだわりでもあります
しかしこの伊吹大根、ただ辛いだけではないのです!
前澤さんの畑周辺は、水分の少ない赤土で出来ており、

この土壌のおかげで、他に栽培している山芋やゴボウ、ホウレンソウには
とても甘みがあるといいます。
その例に漏れず、伊吹大根にも甘みが多く含まれています
伊吹大根に熱を加えると、
それまでの辛みが一転して甘みに変わるのです

引き続きレシピのコーナーで前澤さんに作っていただいた
伊吹大根のステーキも、とても甘みがあって美味しかったです

伊吹大根は、これからの冬の時期が収穫の最盛期。
しかし伊吹山の麓にある畑には毎年2~3mの雪 が積もります。
が積もります。

もちろん畑は積もった雪の真下にあるので、掘り出すのもひと苦労
(大雪のときは、人の背丈くらいの深さまで掘り下げて穫るんだとか )
)
おまけに、普段は歩けば15分のところを、
雪道ともなると優に1時間 はかかり、
はかかり、
しかもその中を、伊吹大根を積んだソリを引いていくそうです。
前澤さんをはじめ、この界隈の農家の方は、
代々そうやって伊吹大根を育てて来られたわけで、
「辛(から)い大根」は「辛(つら)い大根」
でもあったのです。
しかし「辛い大根」は、農家のみなさんの熱意によって、
「美味しい大根」へと生長していくのでした…
名前からも分かるように、滋賀県北東部にある
県内で一番高い伊吹山(1377m)の一帯で栽培されています。
古くは江戸時代の書物にもその名が記されているという伊吹大根は、
「峠の大根」として、現在の米原市大久保地区(旧伊吹町)周辺で
主に自家用に小規模で栽培されてきた作物だそうです。
しかし品種改良された大根が普及すると、
伊吹大根を栽培する農家は減少
 していったといいます。
していったといいます。そんな中、生産者の前澤 静尾さんは、
この伊吹大根の種を守り、現在まで栽培を続けて来られました

栽培歴はもう50年を数えるそうです!

伊吹大根の最大の特徴は、やはり何といっても辛み!
特に大根おろしにすると、さらに辛みが際立ち、
同じく伊吹名産の「伊吹そば」との相性はバツグン


前澤さんの話では
「平地ではなかなかこの辛みは出ない」のだとか。
標高が高い所は昼夜の気温差があり、
平地の大根に比べてゆっくり生長することで
辛みの強い大根が出来るそうです。
またこの短小で寸胴な形も、辛みにとっては重要で、
大きくなればなるほど、辛みは薄まっていくのです。
化学肥料などを与えれば、もっと大きな伊吹大根も穫れるそうですが、
「出来るだけ大きくならないようにする」のが
前澤さんのこだわりでもあります

しかしこの伊吹大根、ただ辛いだけではないのです!
前澤さんの畑周辺は、水分の少ない赤土で出来ており、

この土壌のおかげで、他に栽培している山芋やゴボウ、ホウレンソウには
とても甘みがあるといいます。
その例に漏れず、伊吹大根にも甘みが多く含まれています

伊吹大根に熱を加えると、
それまでの辛みが一転して甘みに変わるのです

引き続きレシピのコーナーで前澤さんに作っていただいた
伊吹大根のステーキも、とても甘みがあって美味しかったです


伊吹大根は、これからの冬の時期が収穫の最盛期。
しかし伊吹山の麓にある畑には毎年2~3mの雪
 が積もります。
が積もります。もちろん畑は積もった雪の真下にあるので、掘り出すのもひと苦労

(大雪のときは、人の背丈くらいの深さまで掘り下げて穫るんだとか
 )
)おまけに、普段は歩けば15分のところを、
雪道ともなると優に1時間
 はかかり、
はかかり、しかもその中を、伊吹大根を積んだソリを引いていくそうです。
前澤さんをはじめ、この界隈の農家の方は、
代々そうやって伊吹大根を育てて来られたわけで、
「辛(から)い大根」は「辛(つら)い大根」
でもあったのです。
しかし「辛い大根」は、農家のみなさんの熱意によって、
「美味しい大根」へと生長していくのでした…

時をかける伝統野菜~北之庄菜~
11月23日の放送でご紹介した食材は、北之庄菜でした。

さて、この「北之庄菜」という野菜を知っているという人は
どれくらいいらっしゃるでしょうか?
この北之庄菜は、カブの仲間で
古くは江戸時代から農家の漬物用の食材として
近江八幡市北之庄町の水郷地で作られていました。

戦後、漬物を漬ける家庭が減ってきたことにより
生産が激減し、昭和40年代にはついに自然消滅してしまいました。
それが約10年ほど前、
偶然に北之庄菜の「種」が見つかったことで、
栽培が再開したという歴史を持った、
近江八幡市の伝統野菜です。
現在はVTRにも登場していただいた
「北之庄菜生産グループ 郷の会」のみなさんが、
栽培や種どりなどをして、普及と保存に努めていらっしゃいます。


この北之庄菜は、
地面に埋まっている部分は白いけど、
日が当たる葉の軸や根元の部分は、紫紅色をしていて、

形は、尻の部分が下ぶくれをしているのが特徴と言われています。

どちらかというと、カブというより短い大根のように見えます。
しかし、かつての北之庄菜を知っている人の話では、
もっと小ぶりの、親指大のサイズが主流だったそうです。

今では、消費者のニーズに合わせて、大小さまざまなサイズを栽培しています。

北之庄菜を店頭に並べると、よく「日野菜」(下)と間違われるそうです。

確かに色取りや雰囲気は似ていますよね
でも郷の会のみなさんの話では、形はもちろん、味も全く違うと言います。
味には渋み・深み・甘みがあり、大根よりもキメが細やかで
漬物のほかに、煮込み料理やジュースなどにも適しており、
プロの料理人をして「素晴らしい食材」だと太鼓判をいただいたんだそうです。

しかし北之庄菜を初めて手にした人は、
口々に「どうやって食べればいいの 」と
」と
レシピが分からずに買い控えされてしまうケースも多いのが現状だとか…
今回はグループの皆さんの、ご家庭でのレシピ を提供してもらい、
を提供してもらい、
番組でいくつかご紹介しました(詳しくは各レシピのブログをご覧下さい)
これで北之庄菜をみなさんに知ってもらい、美味しく食べてもらえれば嬉しいです

さて、この「北之庄菜」という野菜を知っているという人は
どれくらいいらっしゃるでしょうか?
この北之庄菜は、カブの仲間で
古くは江戸時代から農家の漬物用の食材として
近江八幡市北之庄町の水郷地で作られていました。
戦後、漬物を漬ける家庭が減ってきたことにより
生産が激減し、昭和40年代にはついに自然消滅してしまいました。
それが約10年ほど前、
偶然に北之庄菜の「種」が見つかったことで、
栽培が再開したという歴史を持った、
近江八幡市の伝統野菜です。
現在はVTRにも登場していただいた
「北之庄菜生産グループ 郷の会」のみなさんが、
栽培や種どりなどをして、普及と保存に努めていらっしゃいます。


この北之庄菜は、
地面に埋まっている部分は白いけど、
日が当たる葉の軸や根元の部分は、紫紅色をしていて、
形は、尻の部分が下ぶくれをしているのが特徴と言われています。
どちらかというと、カブというより短い大根のように見えます。
しかし、かつての北之庄菜を知っている人の話では、
もっと小ぶりの、親指大のサイズが主流だったそうです。
今では、消費者のニーズに合わせて、大小さまざまなサイズを栽培しています。

北之庄菜を店頭に並べると、よく「日野菜」(下)と間違われるそうです。
確かに色取りや雰囲気は似ていますよね

でも郷の会のみなさんの話では、形はもちろん、味も全く違うと言います。
味には渋み・深み・甘みがあり、大根よりもキメが細やかで
漬物のほかに、煮込み料理やジュースなどにも適しており、
プロの料理人をして「素晴らしい食材」だと太鼓判をいただいたんだそうです。

しかし北之庄菜を初めて手にした人は、
口々に「どうやって食べればいいの
 」と
」とレシピが分からずに買い控えされてしまうケースも多いのが現状だとか…
今回はグループの皆さんの、ご家庭でのレシピ
 を提供してもらい、
を提供してもらい、番組でいくつかご紹介しました(詳しくは各レシピのブログをご覧下さい)
これで北之庄菜をみなさんに知ってもらい、美味しく食べてもらえれば嬉しいです