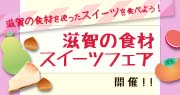母の恵み~大中のニンジン~
11月16日の放送でご紹介した食材は、ニンジンでした。
生産者は、こちらの岡 三木枝さんです。

岡さんのニンジンのお話しを伺うと、
周りの農家仲間のみなさんは揃って
「岡さんのニンジンは、とにかく甘い!」とおっしゃいます。

岡さんのニンジンを使って料理すると、砂糖が少なくて済むんだとか!
岡さん自身も、そう言われて実際に糖度計で計ってみたところ、
糖度が9度あったそうです。
(参考:柑橘類で約10度と言われています)
平均的なニンジンの糖度は、4~5度だそうなので、
いかに甘いかが分かりますよね
なぜそんなに甘いニンジンが出来るのか秘訣を伺ってみましたが、
「これといって特別なことはしてないんやけどねぇ」とのお返事。
強いて挙げれば、「土壌と品種選びが良かったのかな? 」
」

土壌といえば、
岡さんの広大な畑は、大中干拓地の中にあります。

※大中干拓地とは、
戦後、農地拡大のため、内湖である大中の湖を干拓して出来た
11.5キロ平方メートルに及ぶ土地

お話しを伺ってみると、
岡さんご夫婦は、この干拓地に入植した最初の世代なんだそうです。
入植当時は稲作を、
そして政府の減反政策以降は、畑作をしてきたという岡さんご夫婦の歴史は、
そのまま大中干拓地の歴史といってもいいでしょう。

「当時は20代前半で、一番若かったのよ(笑)」
そうチャーミングに語ってくださる姿が、とても可愛らしかったです
女性の生産者としては、
第2回のキュウリの生産者・大崎さん以来、2人目ということになります。
いつも生産者の方への取材では、
栽培のご苦労やこだわり、美味しさのヒミツなどを伺っていますが、
今回、岡さんにインタビューしていると、
やはり女性の生産者だなぁと思う時がありました。
穫れた野菜の大きさに差があったとき、
男性の生産者だと、
ふつうに「大きいのも穫れれば、小さいのもある」と言われますが、
岡さんは
「小さい子もあれば、大きい子もある。人間と一緒」
と表現されていましたし、

種播きしてニンジンが土中で生長する様子も
「赤ちゃんがお母さんのお腹のなかですくすく大きくなるよう」
という例え方をされていたのがとても印象的でした。

植物を育む土や田畑を「母なる大地」と、よく表現しますが、
それを見守る生産者も、また「母」なんだなぁと実感しました
生産者は、こちらの岡 三木枝さんです。
岡さんのニンジンのお話しを伺うと、
周りの農家仲間のみなさんは揃って
「岡さんのニンジンは、とにかく甘い!」とおっしゃいます。
岡さんのニンジンを使って料理すると、砂糖が少なくて済むんだとか!
岡さん自身も、そう言われて実際に糖度計で計ってみたところ、
糖度が9度あったそうです。
(参考:柑橘類で約10度と言われています)
平均的なニンジンの糖度は、4~5度だそうなので、
いかに甘いかが分かりますよね

なぜそんなに甘いニンジンが出来るのか秘訣を伺ってみましたが、
「これといって特別なことはしてないんやけどねぇ」とのお返事。
強いて挙げれば、「土壌と品種選びが良かったのかな?
 」
」土壌といえば、
岡さんの広大な畑は、大中干拓地の中にあります。

※大中干拓地とは、
戦後、農地拡大のため、内湖である大中の湖を干拓して出来た
11.5キロ平方メートルに及ぶ土地
お話しを伺ってみると、
岡さんご夫婦は、この干拓地に入植した最初の世代なんだそうです。
入植当時は稲作を、
そして政府の減反政策以降は、畑作をしてきたという岡さんご夫婦の歴史は、
そのまま大中干拓地の歴史といってもいいでしょう。
「当時は20代前半で、一番若かったのよ(笑)」
そうチャーミングに語ってくださる姿が、とても可愛らしかったです

女性の生産者としては、
第2回のキュウリの生産者・大崎さん以来、2人目ということになります。
いつも生産者の方への取材では、
栽培のご苦労やこだわり、美味しさのヒミツなどを伺っていますが、
今回、岡さんにインタビューしていると、
やはり女性の生産者だなぁと思う時がありました。
穫れた野菜の大きさに差があったとき、
男性の生産者だと、
ふつうに「大きいのも穫れれば、小さいのもある」と言われますが、
岡さんは
「小さい子もあれば、大きい子もある。人間と一緒」

と表現されていましたし、
種播きしてニンジンが土中で生長する様子も
「赤ちゃんがお母さんのお腹のなかですくすく大きくなるよう」

という例え方をされていたのがとても印象的でした。
植物を育む土や田畑を「母なる大地」と、よく表現しますが、
それを見守る生産者も、また「母」なんだなぁと実感しました

自然の“味力(みりょく)”~なめこ と しいたけ~
11月9日の放送は、
今の季節にピッタリの山の幸・しいたけとなめこをご紹介しました。

見てください!この傘の大きなキノコたち
特になめこ(左)なんか、
そこいらのスーパーではお目にかかれないビッグサイズ!
普通イメージする市販のなめこって、
味噌汁に入っている、小指くらいの大きさですもんね。

(周囲に見せても最初なめこと気付かれませんでした )
)
では、なぜこんなに大きさが違うのか

生産者の川村長太郎さんによると、
それは栽培方法が違うから!

スーパーで売られている小さいサイズのキノコは、
主に瓶などに菌を入れて繁殖させる「菌床栽培」という方法ですが、
川村さんのキノコは、
ナラやホオの丸太木に菌を植えて育てる
「原木栽培」で作られているんです。

原木栽培の方が、傘も大きく、味もキノコ本来の味が出るそうで、
原木栽培は、川村さんのこだわりだといいます。

春に植菌し、1年以上ゆっくりと自然の中で寝かせ、
翌年の夏過ぎにようやく芽を出すというサイクルで栽培するので、
今年収穫する分は、実は昨年準備したもの。

どんなキノコに育ってくれるのか、1年間楽しみなんだそうです
キノコ類は日光を嫌うので、栽培はもっぱら木々に覆われた林の中

なので、猿や鹿といった野生の動物がちょくちょく出現しては、
栽培したキノコを食べてしまいます。
ただ、さすがの動物たちも、なめこだけには手をつけないんだとか。
あのヌメリが嫌なのかなぁ~
ちなみにこの辺りでは熊 も出るそうで、
も出るそうで、
大事な木々の皮をはいでしまうといいます。
なので、あちこちの木に、こうやってテープを巻いて
“くまはぎ”を防止するそうです。

なめこは屋外で一貫して栽培しますが、しいたけはちょっと違います。
しいたけは、収穫時期に水分を含むと、
10日くらいで一気に生育してしまうので、
屋外で雨に当たると、全て一斉に生育してしまいます。
なので、収穫のサイクルに合わせて、必要な分を水槽に浸け、

あとは小屋で発育を管理しているそうです。

(小屋の中なので、獣害にも遭いにくい )
)

それにしても、大きい!
しいたけは塩で焼くに限ると、
川村さんが撮影の合間に振舞って下さいました。

道の駅の朝市でも時折こうやってお客さんに振舞っているそうで、
しいたけ嫌いな子どもが「美味しい!」と、
その場でしいたけをママにおねだり していたそうです。
していたそうです。
うん!その気持ち、分かるなぁ~
今の季節にピッタリの山の幸・しいたけとなめこをご紹介しました。
見てください!この傘の大きなキノコたち

特になめこ(左)なんか、
そこいらのスーパーではお目にかかれないビッグサイズ!
普通イメージする市販のなめこって、
味噌汁に入っている、小指くらいの大きさですもんね。

(周囲に見せても最初なめこと気付かれませんでした
 )
)では、なぜこんなに大きさが違うのか


生産者の川村長太郎さんによると、
それは栽培方法が違うから!
スーパーで売られている小さいサイズのキノコは、
主に瓶などに菌を入れて繁殖させる「菌床栽培」という方法ですが、
川村さんのキノコは、
ナラやホオの丸太木に菌を植えて育てる
「原木栽培」で作られているんです。

原木栽培の方が、傘も大きく、味もキノコ本来の味が出るそうで、
原木栽培は、川村さんのこだわりだといいます。

春に植菌し、1年以上ゆっくりと自然の中で寝かせ、
翌年の夏過ぎにようやく芽を出すというサイクルで栽培するので、
今年収穫する分は、実は昨年準備したもの。
どんなキノコに育ってくれるのか、1年間楽しみなんだそうです

キノコ類は日光を嫌うので、栽培はもっぱら木々に覆われた林の中


なので、猿や鹿といった野生の動物がちょくちょく出現しては、
栽培したキノコを食べてしまいます。
ただ、さすがの動物たちも、なめこだけには手をつけないんだとか。
あのヌメリが嫌なのかなぁ~

ちなみにこの辺りでは熊
 も出るそうで、
も出るそうで、大事な木々の皮をはいでしまうといいます。
なので、あちこちの木に、こうやってテープを巻いて
“くまはぎ”を防止するそうです。
なめこは屋外で一貫して栽培しますが、しいたけはちょっと違います。
しいたけは、収穫時期に水分を含むと、
10日くらいで一気に生育してしまうので、
屋外で雨に当たると、全て一斉に生育してしまいます。
なので、収穫のサイクルに合わせて、必要な分を水槽に浸け、
あとは小屋で発育を管理しているそうです。
(小屋の中なので、獣害にも遭いにくい
 )
)それにしても、大きい!
しいたけは塩で焼くに限ると、
川村さんが撮影の合間に振舞って下さいました。
道の駅の朝市でも時折こうやってお客さんに振舞っているそうで、
しいたけ嫌いな子どもが「美味しい!」と、
その場でしいたけをママにおねだり
 していたそうです。
していたそうです。うん!その気持ち、分かるなぁ~

東近江市のアンサンブル~米粉のロールケーキ~
11月2日の放送は、
オススメ食材も今までとはちょっと視点を変えてお届けしました。
いつもは、キュウリやナスなどの野菜を筆頭に、
滋賀県産の農畜水産物をご紹介していますが、
今回のオススメは、米粉のロールケーキでした

こちらの米粉ロールケーキは、
東近江市の米粉ロールケーキ専門店「福福(ぷくぷく)」の
山本優子さんが作られました。
子育て中でも何か始めたいと思っていたときに、
家族の勧めでロールケーキ作りをはじめた山本さん。
最初は普通に小麦粉で作っていたそうですが、
この小麦粉が県外産だったため、
これでは道の駅や量販店の地産地消コーナーで
扱ってもらえない ということで、
ということで、
ご実家で栽培されている東近江のこだわり米からできる
米粉に切り替えて完成したのが、この米粉のロールケーキ。
米粉で作ると、かたくてモシャモシャになりやすく
小麦粉で作るより難しいということですが、
福福の米粉ロールケーキは、
ふわふわでもっちりした食感がとても美味しいスイーツでした。
米粉で作ったことで、実は大きな利点も生まれました。
それは、小麦アレルギーの人でも食べられる!
小麦粉を全く使用していないので、
小麦アレルギーの方でも安心して召し上がれます

中身も、春は、いちごロール、
夏は、プリンロールやコーヒーロール、
秋だとフルーツや栗のロールケーキ
そして11月からはサツマイモロールと、
バラエティに富んだ旬なラインナップ。
しかもその素材はどれも山本さんの自宅で採れたものばかり!
なので、中には数量限定のものもあるので、お買い求めはお早めに

福福のHPはコチラ
http://www.rakuten.ne.jp/gold/pukucake/
※福福での店頭販売はありません。
そして、ロールケーキ作りに欠かせない玉子 も、もちろん東近江産。
も、もちろん東近江産。
鈴鹿の山々に囲まれた布引高原養鶏組合で作られています。

この鈴鹿山系の伏流水と、鈴鹿おろしのきれいな空気という環境のもと、
乳酸菌と海藻類を添加した肥料を食べている元気な鶏が、
毎日3万個もの鶏卵を産んでいるそうです

その名も「いきいきたまご」
黄身のプリッとしたきれいな玉子 でした。
でした。

オススメ食材も今までとはちょっと視点を変えてお届けしました。
いつもは、キュウリやナスなどの野菜を筆頭に、
滋賀県産の農畜水産物をご紹介していますが、
今回のオススメは、米粉のロールケーキでした

こちらの米粉ロールケーキは、
東近江市の米粉ロールケーキ専門店「福福(ぷくぷく)」の
山本優子さんが作られました。
子育て中でも何か始めたいと思っていたときに、
家族の勧めでロールケーキ作りをはじめた山本さん。
最初は普通に小麦粉で作っていたそうですが、
この小麦粉が県外産だったため、
これでは道の駅や量販店の地産地消コーナーで
扱ってもらえない
 ということで、
ということで、ご実家で栽培されている東近江のこだわり米からできる
米粉に切り替えて完成したのが、この米粉のロールケーキ。
米粉で作ると、かたくてモシャモシャになりやすく
小麦粉で作るより難しいということですが、
福福の米粉ロールケーキは、
ふわふわでもっちりした食感がとても美味しいスイーツでした。
米粉で作ったことで、実は大きな利点も生まれました。
それは、小麦アレルギーの人でも食べられる!
小麦粉を全く使用していないので、
小麦アレルギーの方でも安心して召し上がれます

中身も、春は、いちごロール、
夏は、プリンロールやコーヒーロール、
秋だとフルーツや栗のロールケーキ
そして11月からはサツマイモロールと、
バラエティに富んだ旬なラインナップ。
しかもその素材はどれも山本さんの自宅で採れたものばかり!
なので、中には数量限定のものもあるので、お買い求めはお早めに


福福のHPはコチラ
http://www.rakuten.ne.jp/gold/pukucake/
※福福での店頭販売はありません。
そして、ロールケーキ作りに欠かせない玉子
 も、もちろん東近江産。
も、もちろん東近江産。鈴鹿の山々に囲まれた布引高原養鶏組合で作られています。
この鈴鹿山系の伏流水と、鈴鹿おろしのきれいな空気という環境のもと、
乳酸菌と海藻類を添加した肥料を食べている元気な鶏が、
毎日3万個もの鶏卵を産んでいるそうです


その名も「いきいきたまご」
黄身のプリッとしたきれいな玉子
 でした。
でした。
咲いてはいけない つぼみ ~ブロッコリー~
10月26日の放送でご紹介したブロッコリーを栽培されている
松井亮作さんと和代さんご夫妻です。

松井さんは、元々キャベツを栽培していたところ、
キャベツは1玉1玉が大きくて重たく、体力がいるということで、
軽量のブロッコリーの栽培を始めたそうです。
ただ1株1株は小さくても、
収穫・出荷となれば、それなりの重労働には違いありません。

このときも、ご夫婦で仲睦まじく出荷作業をされていました

ブロッコリーは、
食材としてはとてもポピュラーですが、
これまでの生産者への取材を踏まえても、
ブロッコリーを栽培をされているという方は、
ネギとかニンジンなどに比べると、意外と少ない印象
今回訪れた長浜市湖北町界隈でも、
5~6世帯が取り組んでいらしゃるくらいで、
これから地元産の野菜として力を入れていきたい ところだそうです。
ところだそうです。

ふだん食卓に並ぶブロッコリーといえば、だいたいこんな大きさですが、

実際、畑になっているブロッコリーはというと、こんな大きさ

手に持ってみると、
大きさは花嫁さんのブーケ くらいはあるでしょうか。
くらいはあるでしょうか。
畑でブロッコリーを見た第一印象は、
キャベツに似てる!!


(上)ブロッコリー (下)キャベツ
大きな葉っぱに包まれた感じとか、どことなく似ていませんか
それもそのはず!
調べてみると、ブロッコリーとキャベツは
元は同じ植物から生まれた野菜だというです

(※カリフラワーもこの種類に属します)
キャベツは、
葉の部分 を食べるように改良されたのに対して、
を食べるように改良されたのに対して、
ブロッコリーは、
つぼみや茎の部分 を食べるように改良されて出来た野菜なんです。
を食べるように改良されて出来た野菜なんです。
ん? つぼみ?
そう 「これぞブロッコリー」ともいうべき、この緑色の部分は、
「これぞブロッコリー」ともいうべき、この緑色の部分は、
1つ1つが「花蕾(からい)」という、小さなつぼみなんです!

つぼみということは、当然、花が咲きます。
ブロッコリーをそのままにしておくと、
花蕾はだんだん黄色くなり、やがて小さくて白い花 を咲かせます。
を咲かせます。
でも花が咲いてしまうと、ブロッコリーとしては出荷できません
なので花蕾が開く直前の適期を見定めて収穫をしているそうです。
栽培歴20年の松井さんともなると、
一目見ただけで「あとどれくらいで咲き出すのか」が分かるんだとか

ここまで太くて立派な茎と、
きれいなドーム型をした花蕾部分を作るのに欠かせないのが、水分と肥料。
水はたっぷりと、多いときには朝・夜の2回与え、
肥料も有機肥料の鶏フンを与えることで、甘みも出て評判とのこと。
11月からは地元の学校給食 への提供も始まるそうで、
への提供も始まるそうで、
ブロッコリーが苦手な子どもたち にも、
にも、
是非美味しく食べてもらいたいと思います
最後に、今回の取材では、松井さんのほかに、
同じくブロッコリー生産者の中川徳一さんにも取材にご協力いただきました。
ありがとうございました
松井亮作さんと和代さんご夫妻です。
松井さんは、元々キャベツを栽培していたところ、
キャベツは1玉1玉が大きくて重たく、体力がいるということで、
軽量のブロッコリーの栽培を始めたそうです。
ただ1株1株は小さくても、
収穫・出荷となれば、それなりの重労働には違いありません。
このときも、ご夫婦で仲睦まじく出荷作業をされていました

ブロッコリーは、
食材としてはとてもポピュラーですが、
これまでの生産者への取材を踏まえても、
ブロッコリーを栽培をされているという方は、
ネギとかニンジンなどに比べると、意外と少ない印象

今回訪れた長浜市湖北町界隈でも、
5~6世帯が取り組んでいらしゃるくらいで、
これから地元産の野菜として力を入れていきたい
 ところだそうです。
ところだそうです。
ふだん食卓に並ぶブロッコリーといえば、だいたいこんな大きさですが、

実際、畑になっているブロッコリーはというと、こんな大きさ


手に持ってみると、
大きさは花嫁さんのブーケ
 くらいはあるでしょうか。
くらいはあるでしょうか。畑でブロッコリーを見た第一印象は、
キャベツに似てる!!
(上)ブロッコリー (下)キャベツ
大きな葉っぱに包まれた感じとか、どことなく似ていませんか

それもそのはず!
調べてみると、ブロッコリーとキャベツは
元は同じ植物から生まれた野菜だというです


(※カリフラワーもこの種類に属します)
キャベツは、
葉の部分
 を食べるように改良されたのに対して、
を食べるように改良されたのに対して、ブロッコリーは、
つぼみや茎の部分
 を食べるように改良されて出来た野菜なんです。
を食べるように改良されて出来た野菜なんです。ん? つぼみ?
そう
 「これぞブロッコリー」ともいうべき、この緑色の部分は、
「これぞブロッコリー」ともいうべき、この緑色の部分は、1つ1つが「花蕾(からい)」という、小さなつぼみなんです!

つぼみということは、当然、花が咲きます。
ブロッコリーをそのままにしておくと、
花蕾はだんだん黄色くなり、やがて小さくて白い花
 を咲かせます。
を咲かせます。でも花が咲いてしまうと、ブロッコリーとしては出荷できません

なので花蕾が開く直前の適期を見定めて収穫をしているそうです。
栽培歴20年の松井さんともなると、
一目見ただけで「あとどれくらいで咲き出すのか」が分かるんだとか


ここまで太くて立派な茎と、
きれいなドーム型をした花蕾部分を作るのに欠かせないのが、水分と肥料。
水はたっぷりと、多いときには朝・夜の2回与え、
肥料も有機肥料の鶏フンを与えることで、甘みも出て評判とのこと。
11月からは地元の学校給食
 への提供も始まるそうで、
への提供も始まるそうで、ブロッコリーが苦手な子どもたち
 にも、
にも、是非美味しく食べてもらいたいと思います

最後に、今回の取材では、松井さんのほかに、
同じくブロッコリー生産者の中川徳一さんにも取材にご協力いただきました。
ありがとうございました

万能の代名詞 ~ねぎ~
10/19放送のオススメ食材青ネギを栽培されている
生産者の富田健治さんです。

取材を重ねていると、
定年後に農業を始めた という方によく出会いますが、
という方によく出会いますが、
富田さんは、
「農業は体力がいるから、体力があるうちに 」と、
」と、
10年ほど前に職場を早期退職されて、本格的に農業を始められたという方で、
ねぎ以外にも、白菜や玉ねぎ、キャベツなど、
たくさんの種類の農作物を精力的に栽培されています。
富田さんが栽培されている青ネギは、「香頭ねぎ」という品種。

農業を始めたころに「初心者でも作りやすい 」と勧められて以来、
」と勧められて以来、
ずっとこの品種なんだとか。
香頭ねぎは、普通のねぎよりすこし固く、
味や匂いも、それほど ねぎ臭く はないそうです。
何せ、富田さんの2歳になるお孫さんが
美味しい美味しい と言うくらいですから
と言うくらいですから
ねぎは他の野菜に比べると、寒暖や日照りにも強く、
栽培の手間もかかりにくいとされていますが、
その中でも富田さんが栽培で気をつけている点が、まずは水やり
水が足りないと生長も細く、先も黄色く枯れてきます。
撮影時(10/16)のねぎも、
9月末の台風以来、目立った降雨がなかったため、
水を欲している状態だということでした。

ねぎは、その強い匂いから、
農耕では虫除け作物 として用いられることがあります。
として用いられることがあります。
⇒コンパニオン・プランツ
しかし、中にはそんなねぎを好んで食べる虫もいるので、
防虫対策も欠かせない作業のひとつだそうです。
富田さんは、
1つの根からねぎが3股出ている状態を1本として出荷しています。

(※出荷時は先端の枯れた部分は取り除きます)
中にはひとつの根から4股目が出ていることもあり、
その場合は、いちばん生育の悪い1股を取り除きます。

じゃあ、取り除いた分は捨てちゃうのぉ~
いえいえ、そんなことはありません!!
取り除いたねぎの軸をもう一度植えると、
ねぎは再び生長を続けるのです!(なんという生命力 !)
!)
富田さんいわく「ねぎは捨てるところがない!!」のです。
そういえば、余ったねぎを庭先やプランターで植えている主婦の方が
時折いらっしゃいますが、
それも、こういう点を踏まえた生活の知恵なんですねぇ
まさに、ねぎは万能の代名詞!!

何だか花束 みたい!?
みたい!?
生産者の富田健治さんです。
取材を重ねていると、
定年後に農業を始めた
 という方によく出会いますが、
という方によく出会いますが、富田さんは、
「農業は体力がいるから、体力があるうちに
 」と、
」と、10年ほど前に職場を早期退職されて、本格的に農業を始められたという方で、
ねぎ以外にも、白菜や玉ねぎ、キャベツなど、
たくさんの種類の農作物を精力的に栽培されています。
富田さんが栽培されている青ネギは、「香頭ねぎ」という品種。

農業を始めたころに「初心者でも作りやすい
 」と勧められて以来、
」と勧められて以来、ずっとこの品種なんだとか。
香頭ねぎは、普通のねぎよりすこし固く、
味や匂いも、それほど ねぎ臭く はないそうです。
何せ、富田さんの2歳になるお孫さんが
美味しい美味しい
 と言うくらいですから
と言うくらいですからねぎは他の野菜に比べると、寒暖や日照りにも強く、
栽培の手間もかかりにくいとされていますが、
その中でも富田さんが栽培で気をつけている点が、まずは水やり

水が足りないと生長も細く、先も黄色く枯れてきます。
撮影時(10/16)のねぎも、
9月末の台風以来、目立った降雨がなかったため、
水を欲している状態だということでした。
ねぎは、その強い匂いから、
農耕では虫除け作物
 として用いられることがあります。
として用いられることがあります。⇒コンパニオン・プランツ
しかし、中にはそんなねぎを好んで食べる虫もいるので、
防虫対策も欠かせない作業のひとつだそうです。
富田さんは、
1つの根からねぎが3股出ている状態を1本として出荷しています。
(※出荷時は先端の枯れた部分は取り除きます)
中にはひとつの根から4股目が出ていることもあり、
その場合は、いちばん生育の悪い1股を取り除きます。
じゃあ、取り除いた分は捨てちゃうのぉ~

いえいえ、そんなことはありません!!
取り除いたねぎの軸をもう一度植えると、
ねぎは再び生長を続けるのです!(なんという生命力
 !)
!)富田さんいわく「ねぎは捨てるところがない!!」のです。
そういえば、余ったねぎを庭先やプランターで植えている主婦の方が
時折いらっしゃいますが、
それも、こういう点を踏まえた生活の知恵なんですねぇ

まさに、ねぎは万能の代名詞!!
何だか花束
 みたい!?
みたい!?