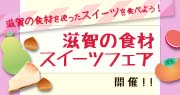虹スポットのトマトは地球を守る(´▽`)?
こんにちは~前田です
先々週は、近江八幡市にある
びわこだいなか愛菜館から生中継をしました
放送時間は5時過ぎからですので、
TVをご覧の皆様には真っ暗な様子しかご覧いただけませんでしたが、
実はあの30分ほど前まではこんな素敵な景色だったんです

きれいな山
また空も雲と光で山のようなきれいな模様
そして左の山の麓にきれいな虹が
この日私は高速道路にのって大津から近江八幡まで向かいましたが、
車の中からも、近江八幡の方向に虹があるのがチラッと見えました
今回のVTRは、びわこだいなか愛菜館横にある、
中江さんのハウスで撮影をしました
この帰り道にも虹が見えたんです
そう、びわこだいなか愛菜館での撮影2回連続の虹だったんです
しかも1回目の日は色んな角度から、3回も


『みさちゃんきっといい事があるヨ 』
』
とスタッフの溝口が言ってくれました
本当 なんかいいことありそう
なんかいいことありそう 楽しみ
楽しみ
ひょっとしたら、びわこだいなか愛菜館は、虹スポットかもしれません









ところで、お伝えしたとおり今回ご紹介したトマトは、
びわこだいなか愛菜館のすぐ隣にあるハウスで栽培されています
私たちは毎週の放送の中で、
食材への生産者さんの愛情や、
様々な調理法を通じて地元産の食材を、
つまり地産地消をススメさせていただいています。
ススメる訳はもちろん、鮮度がよく栄養価が高いことやおいしさ、安全で安心なこと
そして、CO2削減という大切なことを目的としています
今回は、輸送過程でCO2を一切出さずに直売所に並んだトマトをご紹介することができました

このトマトに興味を持って、皆さんが食してくだされば、
ほんの少しだけ、地球を守る役に立つのかな
と思いました


先々週は、近江八幡市にある
びわこだいなか愛菜館から生中継をしました

放送時間は5時過ぎからですので、
TVをご覧の皆様には真っ暗な様子しかご覧いただけませんでしたが、

実はあの30分ほど前まではこんな素敵な景色だったんです


きれいな山

また空も雲と光で山のようなきれいな模様

そして左の山の麓にきれいな虹が

この日私は高速道路にのって大津から近江八幡まで向かいましたが、
車の中からも、近江八幡の方向に虹があるのがチラッと見えました

今回のVTRは、びわこだいなか愛菜館横にある、
中江さんのハウスで撮影をしました

この帰り道にも虹が見えたんです

そう、びわこだいなか愛菜館での撮影2回連続の虹だったんです

しかも1回目の日は色んな角度から、3回も



『みさちゃんきっといい事があるヨ
 』
』とスタッフの溝口が言ってくれました

本当
 なんかいいことありそう
なんかいいことありそう 楽しみ
楽しみ
ひょっとしたら、びわこだいなか愛菜館は、虹スポットかもしれません










ところで、お伝えしたとおり今回ご紹介したトマトは、
びわこだいなか愛菜館のすぐ隣にあるハウスで栽培されています

私たちは毎週の放送の中で、
食材への生産者さんの愛情や、
様々な調理法を通じて地元産の食材を、
つまり地産地消をススメさせていただいています。
ススメる訳はもちろん、鮮度がよく栄養価が高いことやおいしさ、安全で安心なこと
そして、CO2削減という大切なことを目的としています

今回は、輸送過程でCO2を一切出さずに直売所に並んだトマトをご紹介することができました


このトマトに興味を持って、皆さんが食してくだされば、
ほんの少しだけ、地球を守る役に立つのかな
と思いました


愛とこだわりの野菜たち
ひさしぶりの投稿
撮影・編集の奥西です
11月4日の放送で
この「地産地消のススメ」もめでたく20回を迎えました
最近では中継を見学されるギャラリーの方も増えて、
僕たちスタッフも嬉しい限りです
このブログも通算アクセス数が、10,000件を超えました
日ごろから見ていただきありがとうございます
引き続き、番組でもブログでも、
皆さんのお役に立つ情報を発信していきたいと思いますので、
よろしくお願いします
さて、その20回目の放送は
「道の駅 藤樹の里 あどがわ」から
水菜をご紹介しました

今回の生産者・高城恭二さんは、とても勉強熱心で、
番組でも紹介した「コンパニオンプランツ栽培」「不耕起農法」のほか
ビニールハウス内に水を引き入れた「水耕栽培」や
最近はハウスをピンクのシートで覆って、
光合成を促進させる農法を検討するなど、
つねに新しい農法・スタイルを実践していらっしゃいます。

番組をご覧になってない方のために、
VTRで紹介した2つの農法をおさらい

「コンパニオンプランツ栽培」…
和訳の「共栄植物栽培」が示すように、
別々の植物を隣り合わせて植えることで
お互いの成長に良い影響を与えあう栽培方法の1つ。
主に害虫対策に用いられ、キュウリとネギのほかに、
トマトとマリーゴールド、パセリとニンジン等々、
調べてみると、いろいろ組み合わせがあるそうです。

「不耕起農法」…
水田や畑を耕さずに農作物を栽培する農法。
田畑を極力耕さない事で土中の微生物を自然な状態で繁殖させ、
それらの生物による作用で土壌の肥沃化をはかる。
取材に訪れるまで、
こんな農法があるなんて知りませんでした
でも、よくよく調べてみると、
実に理に適った農法だと分かりました。
農業に興味のある方は一度調べてみては
その研究の甲斐もあって、
高城さんの農作物は「高島市農産ブランド認証商品」で
農薬・化学肥料を完全不使用の「ランク1」に認定されています

(おまけに、高城さんは認定者第1号でもあるそうです)
完全不使用の農業は現実的にはなかなか難しい そうですが、
そうですが、
これまで出会った農家さんはどなたも
農薬の使用にはとても気を配ってらっしゃる方ばかり
「環境こだわり農産物」の基準である
通常量の5割以下で取り組んでいらっしゃる方、
子どもがそのまま生食で食べても害が無い程度の
ごくごく微かな量で対応している方…
農家の皆さんの努力と気遣いがあって
食の安全・安心は成り立っているんですね

撮影・編集の奥西です

11月4日の放送で
この「地産地消のススメ」もめでたく20回を迎えました

最近では中継を見学されるギャラリーの方も増えて、
僕たちスタッフも嬉しい限りです

このブログも通算アクセス数が、10,000件を超えました

日ごろから見ていただきありがとうございます

引き続き、番組でもブログでも、
皆さんのお役に立つ情報を発信していきたいと思いますので、
よろしくお願いします

さて、その20回目の放送は
「道の駅 藤樹の里 あどがわ」から
水菜をご紹介しました

今回の生産者・高城恭二さんは、とても勉強熱心で、
番組でも紹介した「コンパニオンプランツ栽培」「不耕起農法」のほか
ビニールハウス内に水を引き入れた「水耕栽培」や
最近はハウスをピンクのシートで覆って、
光合成を促進させる農法を検討するなど、
つねに新しい農法・スタイルを実践していらっしゃいます。

番組をご覧になってない方のために、
VTRで紹介した2つの農法をおさらい

「コンパニオンプランツ栽培」…
和訳の「共栄植物栽培」が示すように、
別々の植物を隣り合わせて植えることで
お互いの成長に良い影響を与えあう栽培方法の1つ。
主に害虫対策に用いられ、キュウリとネギのほかに、
トマトとマリーゴールド、パセリとニンジン等々、
調べてみると、いろいろ組み合わせがあるそうです。
「不耕起農法」…
水田や畑を耕さずに農作物を栽培する農法。
田畑を極力耕さない事で土中の微生物を自然な状態で繁殖させ、
それらの生物による作用で土壌の肥沃化をはかる。
取材に訪れるまで、
こんな農法があるなんて知りませんでした

でも、よくよく調べてみると、
実に理に適った農法だと分かりました。
農業に興味のある方は一度調べてみては

その研究の甲斐もあって、
高城さんの農作物は「高島市農産ブランド認証商品」で
農薬・化学肥料を完全不使用の「ランク1」に認定されています
(おまけに、高城さんは認定者第1号でもあるそうです)
完全不使用の農業は現実的にはなかなか難しい
 そうですが、
そうですが、これまで出会った農家さんはどなたも
農薬の使用にはとても気を配ってらっしゃる方ばかり

「環境こだわり農産物」の基準である
通常量の5割以下で取り組んでいらっしゃる方、
子どもがそのまま生食で食べても害が無い程度の
ごくごく微かな量で対応している方…
農家の皆さんの努力と気遣いがあって
食の安全・安心は成り立っているんですね

タグ :第20回藤樹の里あどがわ(水菜)
フレンドリーなお店
どうもスタッフの小林です
10月7日のオンエアではムラサキイモをご紹介しました
今回の中継先「すまいる市 野洲駅前店」は
番組をご覧になった方はお分かりかと思いますが、
今までで一番コンパクトな店舗でした。

しかし見た目で判断するべからず
店長さん曰く、600種類もの商品を取り扱っているそうで
実際にはとっても品ぞろえ豊富なのです。
本当に野洲駅の目の前という好立地 もあり
もあり
主婦の方はもちろん、
お遣いに来た小学生や会社帰りのサラリーマン、お年寄りなど
幅広い世代の人でにぎわっていました。
今回ご登場いただいたのは、店長の辻村美喜子さん
これまで全16回のオンエアを振り返ってみたら、
初めての女性の店主さんでした。
女性の店長さんのお店だからでしょうか?
取材中に少しおもしろいことに気づきました。
それはすまいる市の値札シールです。




「すまいる市野洲駅前店」の値札ではこのように
生産者のお名前がニックネームで表示されているのです。
辻村店長に理由を伺うと
生産者の方が自由に名前をつけられるようにしているそうで
こうすることで、お客さんも親しみを持ちやすくなり
「今日はけいちゃんのサツマイモある?」
「むっちゃんのトウガラシおいしいわ~」
といった感じに
気に入った生産者の名前をお客さんがすぐに覚えてくれるようになるそうです。
とても画期的でユニークな取り組みですね
もちろん このようなことが出来るのも
このようなことが出来るのも
顔なじみの信頼の出来る生産者さんの野菜を扱っておられる
「すまいる市野洲駅前店」だからこそなのでしょう。
加えて、その名の通り”笑顔 ”の絶えないフレンドリーな店作りを信条とされている
”の絶えないフレンドリーな店作りを信条とされている
「すまいる市」だからこそのアイデアではないでしょうか?
そんなフレンドリーな直売所「すまいる市野洲駅前店」
きっと皆さんもお気に入りの商品が見つかるハズ
野洲にお越しの際は、是非、一度お立ち寄りください

10月7日のオンエアではムラサキイモをご紹介しました
今回の中継先「すまいる市 野洲駅前店」は
番組をご覧になった方はお分かりかと思いますが、
今までで一番コンパクトな店舗でした。
しかし見た目で判断するべからず

店長さん曰く、600種類もの商品を取り扱っているそうで
実際にはとっても品ぞろえ豊富なのです。
本当に野洲駅の目の前という好立地
 もあり
もあり主婦の方はもちろん、
お遣いに来た小学生や会社帰りのサラリーマン、お年寄りなど
幅広い世代の人でにぎわっていました。
今回ご登場いただいたのは、店長の辻村美喜子さん
これまで全16回のオンエアを振り返ってみたら、
初めての女性の店主さんでした。
女性の店長さんのお店だからでしょうか?
取材中に少しおもしろいことに気づきました。
それはすまいる市の値札シールです。
「すまいる市野洲駅前店」の値札ではこのように
生産者のお名前がニックネームで表示されているのです。
辻村店長に理由を伺うと
生産者の方が自由に名前をつけられるようにしているそうで
こうすることで、お客さんも親しみを持ちやすくなり
「今日はけいちゃんのサツマイモある?」
「むっちゃんのトウガラシおいしいわ~」
といった感じに
気に入った生産者の名前をお客さんがすぐに覚えてくれるようになるそうです。
とても画期的でユニークな取り組みですね

もちろん
 このようなことが出来るのも
このようなことが出来るのも顔なじみの信頼の出来る生産者さんの野菜を扱っておられる
「すまいる市野洲駅前店」だからこそなのでしょう。
加えて、その名の通り”笑顔
 ”の絶えないフレンドリーな店作りを信条とされている
”の絶えないフレンドリーな店作りを信条とされている「すまいる市」だからこそのアイデアではないでしょうか?
そんなフレンドリーな直売所「すまいる市野洲駅前店」
きっと皆さんもお気に入りの商品が見つかるハズ

野洲にお越しの際は、是非、一度お立ち寄りください

めっちゃおいしがうれしが☆Max Value
先日放送したマックスバリュ東近江店は、
めっちゃおいしがうれしががいっぱいです
見てくださ~い




ひゃ~これはシアワセですな
滋賀の魅力がたっぷり
ご家庭用にもプレゼント用にも使えますよ
また、中継の日にはこんなポスターを準備していてくださったんです
ありがとうございました

笑顔がとっても素敵な店長(中央)

納品されている梨の生産者さんも活き活きされてます


ぜひぜひみなさんも
マックスバリュ東近江店へ
お買い物に行ってみてください
おいしがうれしがの魅力が
たっぷり ですよ
ですよ
めっちゃおいしがうれしががいっぱいです

見てくださ~い

ひゃ~これはシアワセですな

滋賀の魅力がたっぷり

ご家庭用にもプレゼント用にも使えますよ

また、中継の日にはこんなポスターを準備していてくださったんです

ありがとうございました

笑顔がとっても素敵な店長(中央)
納品されている梨の生産者さんも活き活きされてます

ぜひぜひみなさんも
マックスバリュ東近江店へ
お買い物に行ってみてください

おいしがうれしがの魅力が
たっぷり
 ですよ
ですよ
軟弱野菜を前にして
撮影・編集の奥西です
9月23日の放送ではコマツナと、
生産者の松井康浩さんをご紹介しました。

事前に取材をさせていただいた際に、
松井さんたち生産者の方は
コマツナやホウレンソウのことを総称して
「軟弱野菜」と呼んでいらっいました。
軟弱な野菜 弱っちい
弱っちい
まぁ確かにダイコンやニンジンといった根菜類よりは
葉物で柔らかくフニャフニャしてるけど…
いやいや、そういう「弱い」意味ではないそうです
軟弱野菜とは、
「収穫してから急速にいたみ始める野菜」を指す言葉
と事典にはあります。
畑に植わってるときはみずみずしくても、
収穫したら急速に鮮度が落ち始め 、保存も長くは出来ない
、保存も長くは出来ない
なので、すぐに出荷して店頭に並べなくてはいけない
そういう意味合いで「軟弱」と言われるわけです。
遠い産地からはるばるやって来る というよりは、
というよりは、
近郊で栽培されて、地元で消費される
おっ、まさに地産地消!!
みなさん、店頭でコマツナやホウレンソウなど
軟弱野菜 がシャキッとしていたら、すぐ手に取るのをオススメします
がシャキッとしていたら、すぐ手に取るのをオススメします


9月23日の放送ではコマツナと、
生産者の松井康浩さんをご紹介しました。

事前に取材をさせていただいた際に、
松井さんたち生産者の方は
コマツナやホウレンソウのことを総称して
「軟弱野菜」と呼んでいらっいました。
軟弱な野菜
 弱っちい
弱っちい
まぁ確かにダイコンやニンジンといった根菜類よりは
葉物で柔らかくフニャフニャしてるけど…
いやいや、そういう「弱い」意味ではないそうです

軟弱野菜とは、
「収穫してから急速にいたみ始める野菜」を指す言葉
と事典にはあります。
畑に植わってるときはみずみずしくても、
収穫したら急速に鮮度が落ち始め
 、保存も長くは出来ない
、保存も長くは出来ない
なので、すぐに出荷して店頭に並べなくてはいけない

そういう意味合いで「軟弱」と言われるわけです。
遠い産地からはるばるやって来る
 というよりは、
というよりは、近郊で栽培されて、地元で消費される

おっ、まさに地産地消!!
みなさん、店頭でコマツナやホウレンソウなど
軟弱野菜
 がシャキッとしていたら、すぐ手に取るのをオススメします
がシャキッとしていたら、すぐ手に取るのをオススメします

タグ :第14回コープぜぜ(コマツナ)