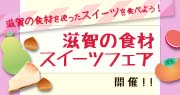D.I.Y.
撮影・編集の奥西です
9月16日のオンエアでは、もち米、
そしてもち米から作られるあられ・おかきをご紹介しました。

今回の生産者・西村至さんは、
あられ屋でありながら、もち米生産者でもあります。
それを表すのが西村さんのお店「八荒堂」の看板です

「米作りから、あられ造りまで」
こだわりぬいた原料は西村さん自身の手で
手塩にかけて 作られているのです
作られているのです
お手製なのは、なにも食糧だけではありません

焼き網、これも西村さんの手作り

天井に開いたこの穴も、2階の加工場の音を下で聞き取るためのひと工夫

更には、かきもちを作る一連の機械類も、八荒堂仕様のオーダーメイド
八荒堂には既製品というのがほとんどありません
よりよい商品を作るためには、
妥協せず、無いものは自分で作る!
これこそまさにDIY(=Do It Yourself;自分でやる)
お話をうかがう中で何度
「これも西村さんが作られたんですか 」と聞き返したことか…
」と聞き返したことか…
ところで、大津市小野にある小野神社って、みなさんご存じですか?
この神社は日本でも唯一の餅の神様を祭った神社なんだそうですが、
西村さんの餅は毎年ここに奉納されているそうです。

滋賀県が餅の発祥にゆかりがあるとは恥ずかしながら知りませんでした
だから「滋賀羽二重糯(もち)」といった
有名なもち米ブランドがあったりするんでしょうね

↑↑「滋賀羽二重糯(もち)」を使用した米粉

9月16日のオンエアでは、もち米、
そしてもち米から作られるあられ・おかきをご紹介しました。
今回の生産者・西村至さんは、
あられ屋でありながら、もち米生産者でもあります。
それを表すのが西村さんのお店「八荒堂」の看板です
「米作りから、あられ造りまで」
こだわりぬいた原料は西村さん自身の手で
手塩にかけて
 作られているのです
作られているのです
お手製なのは、なにも食糧だけではありません
焼き網、これも西村さんの手作り

天井に開いたこの穴も、2階の加工場の音を下で聞き取るためのひと工夫

更には、かきもちを作る一連の機械類も、八荒堂仕様のオーダーメイド

八荒堂には既製品というのがほとんどありません

よりよい商品を作るためには、
妥協せず、無いものは自分で作る!
これこそまさにDIY(=Do It Yourself;自分でやる)

お話をうかがう中で何度
「これも西村さんが作られたんですか
 」と聞き返したことか…
」と聞き返したことか…ところで、大津市小野にある小野神社って、みなさんご存じですか?
この神社は日本でも唯一の餅の神様を祭った神社なんだそうですが、
西村さんの餅は毎年ここに奉納されているそうです。
滋賀県が餅の発祥にゆかりがあるとは恥ずかしながら知りませんでした

だから「滋賀羽二重糯(もち)」といった
有名なもち米ブランドがあったりするんでしょうね

↑↑「滋賀羽二重糯(もち)」を使用した米粉
野洲のイチジクの顔
撮影・編集の奥西です
9月9日の放送では、イチジクと、

生産者の坂口哲哉さんをご紹介しました。

みなさん、イチジクの花ってご存知ですか?
「イチジクって漢字で無花果って書くから、花はないんじゃ 」
」
僕もそう思ってました。
今回、イチジクを取り上げるためにいろいろ調べていたら
なんとイチジクに花はあったんです、しかも実の中に!

実を割った中のつぶつぶ1つ1つが花なんです
こういう花の付き方を隠頭花序(いんとうかじょ)と言うそうです。
世の中、珍しいモノがまだまだいっぱいあるんですねぇ


僕たちはVTR撮影の前に
事前に生産者さんの農園を下見させてもらうのですが、
坂口さんのビニールハウスを見学させてもらった時は
まだ8月上旬の暑い盛り で、しかも昼間
で、しかも昼間
閉め切ったハウス内はもうサウナ 状態で、
状態で、
一歩中に入った途端、メガネ やレンズ
やレンズ は曇り、
は曇り、
指をこすれば湿気でヌルッとなるんです
これにはビックリ

↑↑入った途端にこの状態。僕のようなメガネっ子にはもうたまりません
(※ピンボケ写真ではありません;ちなみに枝と手が写っています)

↑↑少し曇りがとれてきた状態(ちょっと朝もやっぽい!?)
果たして、こんな環境で撮影 できるんだろうか?
できるんだろうか?
と、心配 していましたが、
していましたが、
撮影日は朝も早く、少し涼しかったので、
順調に撮影ができました(ホッ )
)

さて、生産者の坂口哲哉さんは
地元では“てっちゃん”の愛称で知られていて、
ご自身のイチジクも「てっちゃんイチジク」として販売されています。

↑↑パッケージには坂口さんの似顔絵のイラストも
また今月からは「てっちゃんイチジク」で作ったジャムを新たに販売されます。
これには坂口さんの奥様・みつ子さんのお名前が記されています。

坂口さんご夫婦が手塩にかけて作られた イチジクを
イチジクを
是非みなさんも味わってみてください
おうみんち 野洲店ほかで売ってまぁ~す。


9月9日の放送では、イチジクと、
生産者の坂口哲哉さんをご紹介しました。
みなさん、イチジクの花ってご存知ですか?
「イチジクって漢字で無花果って書くから、花はないんじゃ
 」
」僕もそう思ってました。
今回、イチジクを取り上げるためにいろいろ調べていたら
なんとイチジクに花はあったんです、しかも実の中に!
実を割った中のつぶつぶ1つ1つが花なんです

こういう花の付き方を隠頭花序(いんとうかじょ)と言うそうです。
世の中、珍しいモノがまだまだいっぱいあるんですねぇ



僕たちはVTR撮影の前に
事前に生産者さんの農園を下見させてもらうのですが、
坂口さんのビニールハウスを見学させてもらった時は
まだ8月上旬の暑い盛り
 で、しかも昼間
で、しかも昼間
閉め切ったハウス内はもうサウナ
 状態で、
状態で、一歩中に入った途端、メガネ
 やレンズ
やレンズ は曇り、
は曇り、指をこすれば湿気でヌルッとなるんです

これにはビックリ

↑↑入った途端にこの状態。僕のようなメガネっ子にはもうたまりません

(※ピンボケ写真ではありません;ちなみに枝と手が写っています)
↑↑少し曇りがとれてきた状態(ちょっと朝もやっぽい!?)
果たして、こんな環境で撮影
 できるんだろうか?
できるんだろうか?と、心配
 していましたが、
していましたが、撮影日は朝も早く、少し涼しかったので、
順調に撮影ができました(ホッ
 )
)さて、生産者の坂口哲哉さんは
地元では“てっちゃん”の愛称で知られていて、
ご自身のイチジクも「てっちゃんイチジク」として販売されています。
↑↑パッケージには坂口さんの似顔絵のイラストも
また今月からは「てっちゃんイチジク」で作ったジャムを新たに販売されます。
これには坂口さんの奥様・みつ子さんのお名前が記されています。
坂口さんご夫婦が手塩にかけて作られた
 イチジクを
イチジクを是非みなさんも味わってみてください

おうみんち 野洲店ほかで売ってまぁ~す。
市場最大の作戦
撮影・編集の奥西です
カレンダーもいよいよ9月に突入しましたね
“食欲の秋”僕らの番組には打ってつけの季節かな
さてこれまで直売所を主に取り上げてきましたが、
9月2日の放送では量販店 &市場
&市場 をご紹介しました。
をご紹介しました。
(しかもオンエア当日は台風 も直撃…)
も直撃…)


当然ながら、量販店にしろ市場にしろ
自県・他府県問わず全国から品物が入って来る わけですが、
わけですが、
今回はそんな中で滋賀県産を推進しようとする
市場での地産地消の取り組みを取り上げました。
確かに、同じ滋賀県で生産している品物があるなら、
わざわざ他府県の物ではなく、自県の物を買う方がいいですよね
まさに「地産地消のススメ」
その中で今回白羽の矢が立ったのが、カボチャ
市場の方もさることながら、生産者の方も
市場に対して安定した供給ができると、
この取り組みに期待されていました。

↑↑生産者の長田亮さん(JAグリーン近江 かぼちゃ生産部会 副会長)
皆さんも店頭でカボチャを手にされた時は
近江のカボチャかどうかチェックしてみては
そしてどうぞ近江のカボチャをごひいきに

ところで、市場へ撮影に行った時はちょうど“お盆”の時期でした。
そこで聞いたこぼれ話 を1つ。
を1つ。
漁師さん は「お正月休み以上にお盆休みをしっかり取る」んだとか。
は「お正月休み以上にお盆休みをしっかり取る」んだとか。
どうして
「お盆の時期は、漁師さんも殺生したくないからねぇ」
なるほど
ただ機械的に獲るのではなく、魚への敬意の姿勢が見えた瞬間でした。

カレンダーもいよいよ9月に突入しましたね

“食欲の秋”僕らの番組には打ってつけの季節かな

さてこれまで直売所を主に取り上げてきましたが、
9月2日の放送では量販店
 &市場
&市場 をご紹介しました。
をご紹介しました。(しかもオンエア当日は台風
 も直撃…)
も直撃…)当然ながら、量販店にしろ市場にしろ
自県・他府県問わず全国から品物が入って来る
 わけですが、
わけですが、今回はそんな中で滋賀県産を推進しようとする
市場での地産地消の取り組みを取り上げました。
確かに、同じ滋賀県で生産している品物があるなら、
わざわざ他府県の物ではなく、自県の物を買う方がいいですよね

まさに「地産地消のススメ」

その中で今回白羽の矢が立ったのが、カボチャ
市場の方もさることながら、生産者の方も
市場に対して安定した供給ができると、
この取り組みに期待されていました。
↑↑生産者の長田亮さん(JAグリーン近江 かぼちゃ生産部会 副会長)
皆さんも店頭でカボチャを手にされた時は
近江のカボチャかどうかチェックしてみては

そしてどうぞ近江のカボチャをごひいきに

ところで、市場へ撮影に行った時はちょうど“お盆”の時期でした。
そこで聞いたこぼれ話
 を1つ。
を1つ。漁師さん
 は「お正月休み以上にお盆休みをしっかり取る」んだとか。
は「お正月休み以上にお盆休みをしっかり取る」んだとか。どうして

「お盆の時期は、漁師さんも殺生したくないからねぇ」
なるほど

ただ機械的に獲るのではなく、魚への敬意の姿勢が見えた瞬間でした。
ナスのお仕事
撮影・編集の奥西です
先月8月26日のオンエアで、
当コーナーもようやく10回目を迎えました
ここまで番組やブログ 見ていただいた皆さん、ありがとうございます
見ていただいた皆さん、ありがとうございます
そして引き続き、これからもよろしくお願いします
さて記念すべき10回目のオススメ食材は…ナス
ナス?
このコーナーを以前からご存知の方なら
「前にもナスは紹介したやん 」と思われるハズ。
」と思われるハズ。
確かに6月17日のオンエアで、ナスは紹介しました
http://oishigaureshiga.shiga-saku.net/d2011-06-17_1.html

でも今回のナスは、ナスはナスでも
「賀茂ナス」と「水ナス(泉州絹皮水ナス)」です。

↑↑<右上>賀茂ナス(俗にいう丸ナス)、<右下>水ナス、
<左> 千両ナス(※ごく一般的なナス品種)
今回ご紹介した生産者の平井良行さんは、
京都や大阪の特産物だったこれらのナスを
滋賀県での栽培に成功 された方です。
された方です。
平井さんの農園では、ナスは水田の中で作られています。
何でも、水を好むナスは水 をいっぱい吸うので、
をいっぱい吸うので、
手間や効率を考えると、水田は最適な環境なんだそうです。

野菜=畑と思っていた僕には、目からウロコ でした
でした
ただ水田なので、足はとられます…

「ハマっちゃった…ぬ、抜けない」
肉厚な賀茂ナスと、水気を含んでやわらかい水ナス。
全然タイプが違うナスだから、育て方も違うのかと思いきや、
こちらの農園ではどちらも同じ手法で栽培しているそうです。

実際、右畝の手前が「水ナス」エリア、
奥が「賀茂ナス」エリアと分かれているだけで、
それ以外の違いはないそうです。
(※ちなみに千両ナスも同じ場所で栽培されています)
でも賀茂ナスはしっかり実がつまっているし、
水ナスは名の通り軽く握れば水分が出るやわらかさ
そんな良い状態 のナスをいつでも消費者の方に届けたいが、
のナスをいつでも消費者の方に届けたいが、
消費者と作り手の需要と供給のタイミングを見計らうのが、
実は意外と難しい、と平井さん。
平井さんは農家さんでありながら、
常にヴィジョンは“ビジネス”前提。
(うかわファームマートの会長さんというのもありますが)
この農業がビジネスとして成立し
地元の経済がどうすれば回るかといったことを
絶えず考えて行動されているそうです。
直売所・うかわファームマートは
そんな平井さんの“発信基地 ”といったところでしょうか。
”といったところでしょうか。

ぜひ一度みなさんも訪れてみては?
実際の平井さんは、とてもお茶目で気さくな“おっちゃん”です


先月8月26日のオンエアで、
当コーナーもようやく10回目を迎えました

ここまで番組やブログ
 見ていただいた皆さん、ありがとうございます
見ていただいた皆さん、ありがとうございます
そして引き続き、これからもよろしくお願いします

さて記念すべき10回目のオススメ食材は…ナス
ナス?
このコーナーを以前からご存知の方なら
「前にもナスは紹介したやん
 」と思われるハズ。
」と思われるハズ。確かに6月17日のオンエアで、ナスは紹介しました

http://oishigaureshiga.shiga-saku.net/d2011-06-17_1.html
でも今回のナスは、ナスはナスでも
「賀茂ナス」と「水ナス(泉州絹皮水ナス)」です。
↑↑<右上>賀茂ナス(俗にいう丸ナス)、<右下>水ナス、
<左> 千両ナス(※ごく一般的なナス品種)
今回ご紹介した生産者の平井良行さんは、
京都や大阪の特産物だったこれらのナスを
滋賀県での栽培に成功
 された方です。
された方です。平井さんの農園では、ナスは水田の中で作られています。
何でも、水を好むナスは水
 をいっぱい吸うので、
をいっぱい吸うので、手間や効率を考えると、水田は最適な環境なんだそうです。
野菜=畑と思っていた僕には、目からウロコ
 でした
でしたただ水田なので、足はとられます…

「ハマっちゃった…ぬ、抜けない」
肉厚な賀茂ナスと、水気を含んでやわらかい水ナス。
全然タイプが違うナスだから、育て方も違うのかと思いきや、
こちらの農園ではどちらも同じ手法で栽培しているそうです。
実際、右畝の手前が「水ナス」エリア、
奥が「賀茂ナス」エリアと分かれているだけで、
それ以外の違いはないそうです。
(※ちなみに千両ナスも同じ場所で栽培されています)
でも賀茂ナスはしっかり実がつまっているし、
水ナスは名の通り軽く握れば水分が出るやわらかさ
そんな良い状態
 のナスをいつでも消費者の方に届けたいが、
のナスをいつでも消費者の方に届けたいが、消費者と作り手の需要と供給のタイミングを見計らうのが、
実は意外と難しい、と平井さん。
平井さんは農家さんでありながら、
常にヴィジョンは“ビジネス”前提。
(うかわファームマートの会長さんというのもありますが)
この農業がビジネスとして成立し
地元の経済がどうすれば回るかといったことを
絶えず考えて行動されているそうです。
直売所・うかわファームマートは
そんな平井さんの“発信基地
 ”といったところでしょうか。
”といったところでしょうか。ぜひ一度みなさんも訪れてみては?
実際の平井さんは、とてもお茶目で気さくな“おっちゃん”です

そしてカンピョウはつづく
撮影・編集の奥西です
19日のオンエアではカンピョウが作られる過程をご紹介しました。

カンピョウといえば
機械でシュルシュル剥く 光景を
光景を
思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、

当然、電動式の以前は手動器具、
それまた以前は人の手で剥いていたわけです。
あの大きいユウガオの実から、
細長いカンピョウを延々と剥きとる…気の遠くなる作業 です
です

60年以上に及ぶキャリア をお持ちの中尾博次さんともなると、
をお持ちの中尾博次さんともなると、
その遍歴をすべて辿って来られたことでしょう
そんなカンピョウ生産の生き字引・中尾さんが
生産農家の激減 を嘆いておられたのは
を嘆いておられたのは
聞いているコチラとしても、何とも残念でなりませんでした

脈々と続いてきた伝統のカンピョウ生産が
これからまた盛り立っていくことを祈るばかりです
お寿司やおせち料理 などでカンピョウは
などでカンピョウは
“結ぶ”を表す縁起物 として知られていますが、
として知られていますが、

この番組で生産者さん~直売所さん~消費者のみなさんを
結ぶことが出来ていたら幸いです


「これオススメ商品ですって」「僕も買って帰ろうかなぁ?」

19日のオンエアではカンピョウが作られる過程をご紹介しました。
カンピョウといえば
機械でシュルシュル剥く
 光景を
光景を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、
当然、電動式の以前は手動器具、
それまた以前は人の手で剥いていたわけです。
あの大きいユウガオの実から、
細長いカンピョウを延々と剥きとる…気の遠くなる作業
 です
です60年以上に及ぶキャリア
 をお持ちの中尾博次さんともなると、
をお持ちの中尾博次さんともなると、その遍歴をすべて辿って来られたことでしょう
そんなカンピョウ生産の生き字引・中尾さんが
生産農家の激減
 を嘆いておられたのは
を嘆いておられたのは聞いているコチラとしても、何とも残念でなりませんでした

脈々と続いてきた伝統のカンピョウ生産が
これからまた盛り立っていくことを祈るばかりです
お寿司やおせち料理
 などでカンピョウは
などでカンピョウは“結ぶ”を表す縁起物
 として知られていますが、
として知られていますが、この番組で生産者さん~直売所さん~消費者のみなさんを
結ぶことが出来ていたら幸いです

「これオススメ商品ですって」「僕も買って帰ろうかなぁ?」